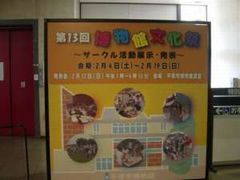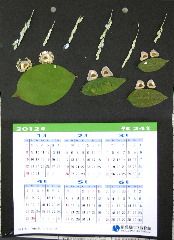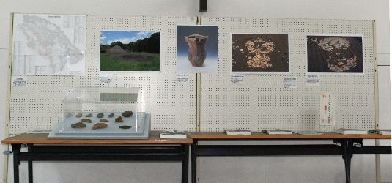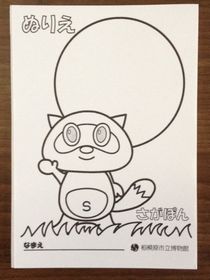全天周映画「はやぶさ」の観覧者が、もうすぐ5万人(平成23年12月)
当館で上映している全天周映画「HAYABUSA BACK TO THE EARTH」の観覧者がもうすぐ5万人になろうとしています。
上坂浩光さん監督のこの映画は2009年に公開され、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に戻った後には「帰還バージョン」が制作・公開されました。当館では2010年1月から「2009年バージョン」の上映を開始し、2011年1月からは「帰還バージョン」を上映してきました。
全編CGで制作されたこの映画は、出演者が「はやぶさ」ただひとりで、あとは篠田三郎さんのナレーションと効果的な音楽と素敵な主題歌というシンプルなものでありながら、優れた科学映画であり、また、多くの人に感動を与える映画でもあります。
映画として優れた作品であることは、「第52回科学技術映像祭」科学教養部門での文部科学大臣賞受賞や「映文連アワード2011」での最優秀作品賞受賞などを見ても明らかです。
ところで、この映画で涙腺の緩んでしまう人が少なからずいます。それは見る人が、擬人化された「はやぶさ」とともに宇宙を旅し、苦難を乗り越える体験を共有するためなのでしょう。そして、その物語の背景には暗く広い宇宙があり、その宇宙を行く小さな探査機の例えようもない孤独があるように感じられます。そこでは、人は寄り添ことを選ぶしかないのでしょう。
この映画が描いた「はやぶさ」のプロジェクトは、そんな途方もなく広い宇宙の中にぽつんと存在する小さな小さな星に探査機が行き、なおかつ地球に帰ってくることを目指したもので、私などには気の遠くなるような計画です。しかし、このプロジェクトにかかわった人々は、永年にわたり叡智を結集し、多くの技術を積み上げ、創造し、そして決してあきらめない心で実現してしまったのです。
さて、当館のスタッフは、この全天周映画を見終わって泣いている子どもを何人も見ています。ある子どもは「はやぶさが燃えてしまってかわいそう」と泣いていました。それを見て、傍らのお父さんが「泣かないでいいんだよ。“はやぶさ”は大事な仕事をちゃんとやり遂げたんだから」と言い、お母さんが「今度はJAXAに燃えない“はやぶさ”を作ってもらおうね」と話しかけている、そんな光景も見ています。
「HAYABUSA BACK TO THE EARTH」の当館の観覧者累計が5万人になろうとする今、この作品と、そして「はやぶさ」のプロジェクトそのものが、どれほど大きな影響を、とりわけ子どもたちに与えたことだろうと、あらためて思っています。(館長)
入館者200万人達成しました!(平成23年8月)
おかげさまで、8月28日(日)に入館者数200万人を達成しました。
200万人目の来場者は、相模原市中央区にお住まいの白川睦生くんです。両親と妹さんの4人で訪れてくれました。「自分が200万人目だったことにびっくりした。博物館には何度も来ているが、200万人というたくさんの人が来ていることに驚いた。」と話してくれました。
エントランスに200万人達成セレモニーのアナウンスが流れると、その場に居合わせた入館者から祝福の拍手が起こりました。白川くんには、加山俊夫相模原市長から花束と記念品(ライト付地球儀/天球儀)が、岡本実教育長から図鑑と「プラネタリウム・全天周映画招待券」が贈られました。
当館は、毎年10万人を超える入館者数がありますが、平成22年6月、小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還したことで、当館で上映された全天周映画「HAYABUSA BACK TO THE EARTH」が好評を博し、さらに「はやぶさ」が持ち帰ったカプセルの世界初展示などにより入館者数が急増、200万人達成が予想より半年ほど早まりました。
遠方からのお客様も増えており、これを契機に一層魅力ある博物館になるよう、スタッフ一同、気持ちを新たに取り組んでいきたいと思っています。(企画情報班 金井)